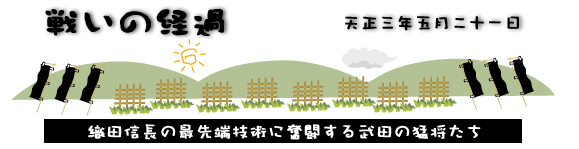
▼歴史を変えた合戦の火蓋が切っておとされた▼
(午前6時ごろ~)
武田軍左翼隊
この度の戦さは当徳川の戦い、上方勢(織田勢)に先を越されたなら徳川家の禍根になろうと考えていた大久保忠世・忠佐隊により火蓋が切られることとなった。
柵の外に歩兵隊ばかりで張り出して敵を待っていた徳川軍大久保隊が武田軍山県昌景隊の前面にいた足軽に対して鉄砲を撃ちかけてきた。
 山県隊はこれを見ると、押し太鼓の音とともについに三千の騎馬隊で川路村連吾橋の南の方、柵のない方へ押し回って(連吾川下流を渡って迂回し)、徳川勢の後方へ出ようとした。
山県隊はこれを見ると、押し太鼓の音とともについに三千の騎馬隊で川路村連吾橋の南の方、柵のない方へ押し回って(連吾川下流を渡って迂回し)、徳川勢の後方へ出ようとした。
これを遮ろうとして立ちはだかったのが、大久保兄弟率いる一隊であった。
その戦いぶりは、敵と味方の間に乱れ入り、敵がかかって来たら柵中に退き鉄砲を放ち、敵が退けば追って出るといった具合に終始接触して離れず、多数の兵を二人の采配で取ってまわす姿はみごとであったという。
9回の競り合いの後戸惑う山県隊は連吾川の深く切り立った断崖にも阻まれ、ついに向こう岸に渡ることができず、この間にも大久保隊三百余挺の銃火に多くの兵を失いながら竹広方面へと転戦していった。
▼さらに両軍の駆け引きが繰り返された▼
(午前7時半ごろ~)
武田軍左翼隊
奮闘しつづけていた山県隊が竹広口方面に転戦していくと、つづいて小幡信貞兵二千余(赤備え)が馬防柵に迫ったが、やはり徳川勢三百挺の鉄砲がいっせいに火を吹いたため、その半数が打ち倒され、残兵は竹広・柳田方面に敗走した。
これにつづいて、小山田信茂が率いる騎馬隊が突撃を敢行したが、これまた馬防柵内からの一斉射撃に妨げられ、多くの兵を失い残兵は敗走した。
しかし、なおも屈せず、こんどは武田信豊の率いる黒備えが出撃し、柵ぎわまで攻め寄せたが雨のように打ち寄せる銃弾のため、こらえきれず退却した。
長篠城包囲軍
 武田軍は急いで攻撃する必要はなかった。なぜならば、連合軍は柵を構築するなど防戦の構えを見せており、全軍が柵から出て突撃してくることはまずないからである。
武田軍は急いで攻撃する必要はなかった。なぜならば、連合軍は柵を構築するなど防戦の構えを見せており、全軍が柵から出て突撃してくることはまずないからである。
しかし、そんな武田軍の裏をかいた出来事が起こった。長篠城の包囲軍として残してきた武田信実らが守る鳶ヶ巣山が酒井忠次らによって奇襲されたのである。(午前8時ごろ)そのとき湧き上がった喚声と噴煙は連合軍の士気を高めるとともに、武田軍の退路を遮断することとなり、大きな不安を与えるとともに勝頼を進軍へと追い詰めることとなった。
武田軍右翼隊
 馬場信春を先手とする武田軍右翼隊も金鼓を打ち鳴らし、信長の本陣を目指して突撃を敢行した。
馬場信春を先手とする武田軍右翼隊も金鼓を打ち鳴らし、信長の本陣を目指して突撃を敢行した。
北方の丸山砦は馬防柵の前に作られた陣地で、信長軍の佐久間信盛が六千の兵力で固めていたが、馬場信春はわずか七百の手勢を二手に分けて攻撃をかけ、激闘の末、ついに佐久間隊を追い落として丸山を占拠した。
しかし、柵へ引き込んだ佐久間を馬場は敢えて追わず、この陣地を最後まで死守した。
馬場隊が他の部隊のように深追いしなかったのは、連合軍の佐久間信盛が裏切るとの調略があったからだといわれている。
▼宿将の進言を受け入れず、勝頼ついに全軍の進軍を命ず▼
(午前10時ごろ~)
武田軍右翼隊
この頃には武田軍が有利な戦の展開をみせていた(というのは連合軍が武田軍をおびきよせるために柵内に引っ込むことを繰り返していたため)。
この状況をみた馬場は勝頼の本陣へ使いを出し、「いま戦いは優勢であるが、敵軍は兵と鉄砲が甚だしい。味方の損傷が少ない今、一応の戦果を挙げ弓矢の面目もたったので、これを機会に退陣されたまえ」と進言した。
これに対し、勝頼は無言のまま無視し、全軍の進撃を命じた。
 馬場は敗戦を覚悟するとともに、同じく武田軍右翼に属する真田信綱・昌輝兄弟・土屋昌次らにこのことを告げた。
馬場は敗戦を覚悟するとともに、同じく武田軍右翼に属する真田信綱・昌輝兄弟・土屋昌次らにこのことを告げた。
これを受け、真田信綱・昌輝兄弟や土屋昌次らは相互に進撃し、馬防柵に迫った。
飛び交う弾丸をかいくぐって、第一柵を破らんとする武田軍の勢いに、信長は急ぎ羽柴秀吉・丹羽長秀の部隊を北側から迂回させ、側面から急激させた。
真田兄弟は敢無く後退したが、その後に続いた土屋昌次は柵前で奮闘した。
まず、柵前にいた滝川一益率いる同じく騎馬隊と合い交え、なんなく打ち破ったが、その背後には三重の柵を備えた鉄砲隊が控えていた。猛烈な勢いで一の柵で鉄砲を撃とうとしていた足軽隊を踏み潰し、次いで二の柵からの一斉射撃で多くの騎馬武者を失いながらもついに二の柵に突破口をあけた。
 ところが、織田軍は少しもあわてず、佐々成政・前田利家らの指揮する鉄砲隊が一斉に火蓋を切り、土屋昌次は三の柵によじ登ったところを撃たれ落命した。
ところが、織田軍は少しもあわてず、佐々成政・前田利家らの指揮する鉄砲隊が一斉に火蓋を切り、土屋昌次は三の柵によじ登ったところを撃たれ落命した。
また、これら右翼の奮戦ぶりを見た中央隊の内藤昌豊らも兵を繰り出し、同じく佐久間・滝川の陣地(右翼隊方面)をめざして突進したが、織田軍の足軽鉄砲隊に苦しめられ、多くの兵を失った。
再び、真田兄弟は二手に分かれ、まず信綱が二百余騎をもって柴田・羽柴隊の柵にめがけ三列縦隊で疾風のような速さで突進していった。柵の内側から撃ちまくっていた鉄砲隊も次の弾丸を詰め込む余裕もなく、圧倒され後退した。そこで柴田・羽柴隊は柵の外の側面に迂回して銃火を浴びせたため、奮闘あえなく信綱は柵前で戦死し、その後に続いた弟昌輝も負傷しやむを得ず退却した。
武田軍中央隊
 勝頼本陣前に布陣した中央隊の使命は、左右部隊の揺さぶりで連合が動揺するところを中央突破することであった。
勝頼本陣前に布陣した中央隊の使命は、左右部隊の揺さぶりで連合が動揺するところを中央突破することであった。
ゆえに左右部隊の戦況を見据え、援軍を繰り出したりしていたが、ついに各隊による攻撃を本格的に開始した。
武田中央隊の内藤昌豊・原昌胤・武田信廉らの軍はよくせり合い、敵の馬防柵の際まで攻め込んだが、惜しくも銃火に撃破されて敗退した。
しかし、内藤隊はこの戦いで六度戦ったといわれ、家康本陣横の八剣前では、錐もみ状態となって馬防柵に殺到し、一の柵・二の柵を踏み破り激しく攻めたてた。さらに、三の柵をも突破して二十余名が敵陣内に押し入り、家康を大いに震え上がらせたといわれる。三の柵が破られたのは記録上、このときだけであった。
▼名将山県昌景力尽き、壮絶な最期を遂げる▼
(午後1時ごろ~)
武田軍右翼隊(生き残り諸隊)
 武田軍右翼の山県隊は、大久保忠世・忠佐兄弟の軍との戦った後、相手の巧みな陽動作戦にかかって柵の背後を衝くことができず、誘い込まれるように中央部の竹広激戦地へ深入りしていった。
武田軍右翼の山県隊は、大久保忠世・忠佐兄弟の軍との戦った後、相手の巧みな陽動作戦にかかって柵の背後を衝くことができず、誘い込まれるように中央部の竹広激戦地へ深入りしていった。
そして、同じ右翼に属する小山田信茂・甘利信康らの生き残り諸隊とともに軍勢を立て直し、押し出てきた丹羽・柴田・羽柴勢を横合いから攻撃して撃退させ、余勢を駆って家康本陣へ果敢な攻撃を仕掛けた。しかし、山県は縦列を構えて待ち受けていた本多忠勝の鉄砲隊の前にあえなく壮絶な最期を遂げた。
この頃から、徳川勢はこれまでの戦法を変え、いち早く柵外に出て攻撃に転じ、これに続いて織田勢も漸次柵外に顕れ、あたかに堤防が切れて流れ出る濁流のごとく敵を前方に圧し、武田軍は圧迫されて一線まで引き下がっていった。
▼信長、総攻撃を命ずる、両軍入り乱れての激戦はじまる▼
そして、勝頼敗走す
(午後2時ごろ~)
勝頼本陣附近
もはや左翼、中央、右翼の区別もない乱軍状態になった武田軍を見て攻撃力の限界と見てとると、ついに信長は総攻撃を命じ、全軍は次々と柵外に進み、連吾川を渡って押し寄せた。このため、これまでの各隊ごとの戦闘とは打って変わり、両軍入り乱れての合戦が始まった。
中央隊の武田信豊隊は押しつ押されつの勇戦ぶりを示したが、滝川一益隊の勢いに押され、退いた。
一条信龍隊、武田信廉隊も退き、踏みとどまっていた小幡信貞隊も敵に包囲され、おびただしい損害を出し、こらえきれず崩れて引いた。
 本陣が騒ぎ立ち、しんがりとなるべく後備にあった穴山信君隊を繰り出そうとしたが、穴山隊はすでに退き始めていた。
本陣が騒ぎ立ち、しんがりとなるべく後備にあった穴山信君隊を繰り出そうとしたが、穴山隊はすでに退き始めていた。
勝頼の後備にあった穴山信君や武田信光らは、敵の旗を見るやいなや、勝頼より先に逃げ去ったという。
勝頼は戦況を見定めるとともに、また多くの武将の戦死を聞き、死を決して戦おうとしたが、家来に止められて、帰還することを決意した。
ついに才ノ神に立てられた「大」の旗が動きはじめた。
武田軍の引き揚げ貝の音が響き、勝頼観戦陣地を下りて、宮脇に出て大海方面に退却を始めた。
▼必死の殿戦のなかで武田宿将が次々と覚悟の最期を遂げる▼
(午後3時ごろ~)
武田軍右翼隊(生き残り諸隊)、中央隊
 その後、甘利、内藤、原などの各隊は勝頼本隊の旗が宮脇方面にのがれていくのを見届けるまでの間、勢いにのって押し寄せる敵をよく支え戦っていた。
その後、甘利、内藤、原などの各隊は勝頼本隊の旗が宮脇方面にのがれていくのを見届けるまでの間、勢いにのって押し寄せる敵をよく支え戦っていた。
左翼隊として山県とともに戦ってきた甘利信康は中央隊と合流した後善戦したが、天王山のふもとまでじりじりと押され、ついに無念の自決を遂げる。
中央隊の原昌胤は殿(しんがり)をつとめ奮戦したが、信玄台地にて自ら敵の銃弾の前に身をさらし落命する。
同じく中央隊として戦った内藤昌豊は、討死の時至れりと数少なくなった残兵と家康本陣めがけて討ちかかっていった。これに対し、家康の側近くを守っていた本多忠勝は自ら槍を取ってこれに立ち向かい、奮闘した。また、榊原康政・大須賀康高の部隊も加わって銃弾や矢を浴びせかけたため、内藤隊の手勢は皆討たれ、昌豊自らも射かけられた矢が全身に突き刺さって蓑のようになり、落馬したところを討ち取られた。
武田軍右翼隊(連合軍追撃戦・橋詰殿戦)
 中央隊が崩され、右翼左翼が分断されたため、敵に囲まれる形勢を見て取った馬場は退却せざるを得なかった。と同時に、勝頼の退路を確保し援護するために、一足早く戦場を離れ、出沢橋詰方面へ向かう。
中央隊が崩され、右翼左翼が分断されたため、敵に囲まれる形勢を見て取った馬場は退却せざるを得なかった。と同時に、勝頼の退路を確保し援護するために、一足早く戦場を離れ、出沢橋詰方面へ向かう。
出沢橋詰で勝頼を出迎えた馬場信春はその退却を見届ると引き返し、橋詰で覚悟の討死をした。
敗れた武田軍は、山へ逃げ込んで餓死する者あり、あるいは先を争い崖や橋(猿橋)から川へ落ちて死ぬ者も際限なく、戦死者の数は主だった将・雑兵合わせて一万余人にのぼった。
しかし、一方の織田徳川連合軍も宿将格の死者はほとんどないが、死傷者六千という数字は決して少ないものではなく、悪条件における武田軍の奮闘ぶりにも注目すべきである。